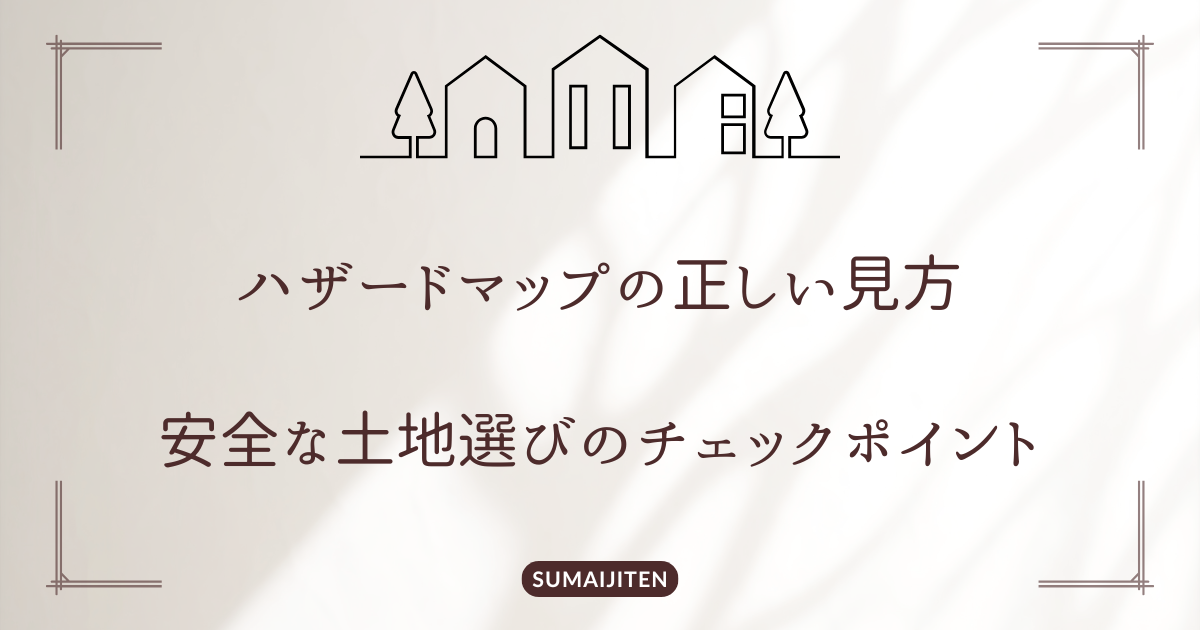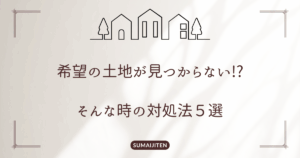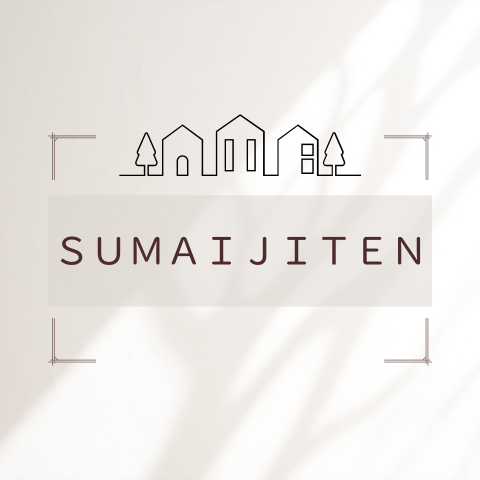はじめに:家を建てる土地、どこを選べばいい?
「この土地、駅チカで価格も手頃。ここに決めちゃおうかな?」
ちょっと待ってください!
その土地、災害に強い場所ですか?
台風や豪雨、地震といった自然災害が全国で多発する中、「災害リスクを正しく知ること」は、家づくりのスタートライン。特に今は、不動産取引時にハザードマップの説明が義務化されているほど、重要な情報なんです。
この記事では、ハザードマップの見方や、災害リスクの判断方法、安全な土地の選び方を、宅建士の視点からわかりやすく解説します!
ハザードマップってそもそも何?
災害に備えるために、各自治体や国が作成しているのが「ハザードマップ」。簡単に言えば「ここが危ないよ」というのを色で示した防災地図です。
種類はいろいろあって、それぞれの災害に応じて分かれています。
主なハザードマップの種類
- 洪水ハザードマップ
⇒ 河川の氾濫でどれくらい浸水するか?がわかる
→ 最大「1000年に1回レベル」の豪雨を想定して色分け - 土砂災害ハザードマップ
⇒ 崖崩れ・土石流・地すべりのリスクを表示
→ 黄色=警戒区域、赤=特別警戒区域 - 津波ハザードマップ
⇒ 津波による浸水想定、避難経路の確認にも使える - 地震ハザードマップ
⇒ 揺れやすさ、液状化しやすいエリアを可視化!
ハザードマップってどこで見られるの?
「見たいけど、どこで手に入るの?」
そんな方に向けて、入手先はこの3つです!
- ✅【国土交通省ポータル】
重ねるハザードマップでは複数の災害を重ねて見られる - ✅【市区町村のホームページ】
地域ごとの詳細マップが掲載されています - ✅【役所の窓口】
都市計画課・防災課などで直接もらえることも!
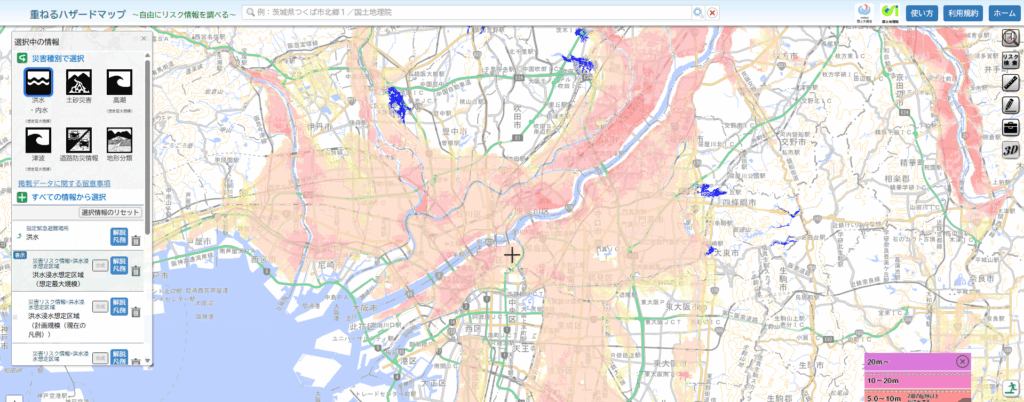
読み方が分かれば怖くない!色の意味をチェック
洪水の場合は「水の深さ」を色で表現
| 色浸水の深さイメージ | ||
| 薄い青 | 0.5m未満 | 膝下程度 |
| 濃い青 | 0.5〜3.0m | 1階が水没するレベル |
| 紫 | 3.0〜5.0m | 1階全没。避難必須! |
| 黒 | 5.0m超 | 2階も危険ゾーン |
「浸水深が深い」「長時間浸水が続く」「近くに川がある」などは要注意サイン!
土砂災害の危険度ってどう見るの?
- 黄色:土砂災害警戒区域(がけ崩れや土石流のおそれ)
- 赤色:特別警戒区域(命の危険レベル)
崖からの距離が近い土地は、警戒レベルも高くなります。
地震ハザードマップのポイント
- 揺れやすさ=地盤の硬さ
- 液状化が起こりやすい場所もチェック!
- 活断層の有無も要確認
「1000年に1回」って本当に起こるの?
「1000年後まで安心ってこと?」…そう思った方、いませんか?
実はこれ、「毎年0.1%の確率で起こる」という意味。つまり、来年起きても不思議じゃないんです!
だから、どんなに確率が低く見えても、油断しないでチェックすることが大事なんですね。
保険もリスクとセットで考えよう
火災保険、水災補償って?
実は、水災(洪水・土砂災害など)はオプション扱いのことも。
- 補償される条件:床上浸水 or 地面から45cm以上
- 補償額の目安:建物価格の70%くらい
- リスクが高い地域=保険料が高くなる傾向も!
地震保険もセットで検討
- 火災保険とセット加入が基本
- 補償額は火災保険の30〜50%
- 耐震等級が高いと保険料も割引されることがあります!
土地選びで意識したい「リスクレベル」
| リスク判断ポイント | |
| 低リスク | ハザードマップで安全ゾーン。標高も高く、過去災害なし |
| 中リスク | 浸水0.5m未満など軽度なリスク。対策すれば◎ |
| 高リスク | 浸水3m超や特別警戒区域。慎重に判断を! |
| 極めて高リスク | 浸水5m超、避難困難、リスク重複 → 回避推奨 |
建てるときにできる対策は?
「少しリスクがあっても、対策すれば住めるかも?」
その通り!建築時に対策することで、リスクを減らすこともできます。
- 💧 洪水対策:基礎の高さを上げる、盛土、防水強化など
- 🪨 土砂対策:擁壁の設置、排水ルートの整備
- 🌍 地震対策:耐震等級3、地盤改良、杭基礎など
対策にはいくらかかるの?
| 項目費用の目安 | |
| 洪水対策(盛土・防水) | 約30〜200万円 |
| 土砂対策(擁壁・排水) | 約50〜200万円 |
| 地震対策(耐震・地盤改良) | 約100〜300万円 |
保険料などを含めた**「総コスト」**で土地を判断しましょう!
まとめ:リスクを知って、後悔しない土地選びを!
最後にお伝えしたいこと。
100%安全な土地なんてないんです。
でも、リスクを正しく知って、対策を講じれば、安全な暮らしは手に入れられます。
ハザードマップを活用して、災害リスクを事前に把握すること。現地で実際に確認して、納得して選ぶこと。
家族の命と未来を守るために、「情報」をしっかり味方につけていきましょう!長期優良住宅とは?認定を受けるメリットと申請の流れ